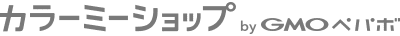☆ドリップ編☆
ここでは、一般的なドリッパーで共通して使える淹れ方をご紹介します。
用意するもの
手順
注湯をゆっくりにすると、しっかりした味わいになりますが、しつこい印象になることもあります。素早く湯を注げば、あっさりした味になりますが、物足りない印象になることも。豆の量を増減してみたり、挽き方を変えてみたり。調整しながら、自分好みの味わいを見つけていくのも楽しいです。
当店では上記のドリップ法をお勧めしていますが、細く途切れずに注ぐ方法や、蒸らし時にスプーンで攪拌する方法などもあります。YouTubeなどで検索してみて下さい。
ここでは、一般的なドリッパーで共通して使える淹れ方をご紹介します。
用意するもの
- ドリッパー
- フィルター
- コーヒーの粉(新鮮な豆を、できれば直前に挽いてください。)
- ドリップポット(口が細いものがお勧めです。)
- サーバー(2杯以上同時に淹れる場合に必要です。1杯の場合はカップに直接ドリッパーを乗せても構いません)
- キッチンスケール
- タイマー(あれば。)

手順
- コーヒー豆を挽く。
豆の量は、当店の基準では
出来上がり150ml 豆11g
200ml 13g
300ml 20g
400ml 25g
としています。この量では濃い、薄いという方は、お好みで豆の量を増減して下さい。
挽き方は中挽きをお勧めしますが、好みで調整して頂いて構いません。荒挽きではよりクリーンな味わいとなりますが、薄くなりがちなので、少し豆の量を増やすと良いでしょう。
細挽きではボディ感が強調されます(いわゆるコクのある味わい)。豆の量は中挽きより若干少なめでOKです。細く挽きすぎると目詰まりして落ちなくなるのでご注意を。

- お湯を沸かす。
十分な量のお湯を沸かします。ポットやカップを温めたい方はその分も忘れず。また、最後にドリッパー内のコーヒー粉に10g〜50gのお湯が吸収され残りますので、余裕をもって多めに沸かしておきましょう。
淹れる温度は、高温になるにつれ、成分が抽出されやすくなるため、苦味、酸味がはっきり感じられます。落ち着いたまろやかな味にしたい場合は、80℃台のお湯を用いてみて下さい。
湯沸し用のやかんからポットにお湯を移すと、湯温はかなり下がります。高温での抽出を好む方は、一度ポットを温めておくと良いでしょう。
カップを温めておくか否かは好みです。熱すぎるとすぐに飲むことができません。また、スペシャルティコーヒーは温度によって表情が変わるため、あえて温めず、温度変化が早く楽しめるようにするのもアリです。
- サーバーやカップの上にドリッパーを置き、フィルターをセットする。
無漂白のフィルターには、紙の味が出やすいものがあります。気になる方は一度お湯をフィルターに満遍なく注ぎ、紙の味を湯で流します。サーバーやカップに落ちたお湯は捨てます。

- 粉をフィルターに入れ、平らにならす。

- 20g程度のお湯(以下湯量は150ml淹れる場合で表記)を、中心から外側にらせんを描くように注ぐ。外側の粉にまでしっかりお湯がいきわたるようにする。

- 30秒蒸らす。
ここで少し待って蒸らすことで、お湯が粉の内部まで浸透し、かつ粉に含まれている炭酸ガスが放出され、抽出準備状態となります。蒸らしを行わないと、風味が十分出ませんので、必ず行って下さい。
- 1投目。30g(スケールで50gになるまで)、蒸らし時同様に中心かららせんを描くように注ぐ。外側の粉にもしっかり注ぎますが、粉より外には注がないようにします。

- 4〜5秒程度待つ。粉の状態にもよりますが、お湯が落ちて、ふくらんでいた粉が平坦になります。そのタイミングで2投目、50g(スケールで100gになるまで)を同様に注ぐ。
- 5〜6秒程度待つ。再び粉が平坦になったら、3投目。同様に60g(スケールで160gになるまで)注ぐ。
- 湯がサーバー(またはカップ)に落ちきったらできあがり。ほぼ150mlのコーヒーができあがっているはずです。
- あとはゆっくりお楽しみ下さい!

注湯をゆっくりにすると、しっかりした味わいになりますが、しつこい印象になることもあります。素早く湯を注げば、あっさりした味になりますが、物足りない印象になることも。豆の量を増減してみたり、挽き方を変えてみたり。調整しながら、自分好みの味わいを見つけていくのも楽しいです。
当店では上記のドリップ法をお勧めしていますが、細く途切れずに注ぐ方法や、蒸らし時にスプーンで攪拌する方法などもあります。YouTubeなどで検索してみて下さい。